ベルリン1919
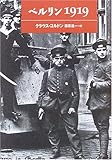
- 作者: クラウスコルドン
- 出版社/メーカー: 理論社
- 発売日: 2006/02
- メディア: 単行本
- クリック: 11回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
なぜ、ぼくたちは争いをやめられないのだろう?ドイツ文学界の巨星コルドンがベルリンを舞台に20世紀激動の時代を描き、そして、戦争と平和を現代に問う大河小説3部作。話題作「ベルリン1933」につながる待望の“第1部”ついに邦訳。
転換期3部作の第一作目。原題は「赤い水兵あるいはある忘れられた冬」。1918年から1919年にかけての冬のベルリンが舞台になっている。
私は受験の時に世界史を選択していたんだけど、情けないことに世界史の記憶がほとんどない。興味を持ってそこに繰り広げられる「物語」を読み解いていかなければ、歴史というのは頭に入ってこないのだろう。多分ここで語られている「革命」については、年号と「革命を起こそうとしたけれど失敗」みたいな理解しかしていなかったんだなと思う。
作者のあとがきによると、この時代のことがドイツの人々の意識にのぼることはほとんどないのだと言う。そのあとのヒトラーの独裁と第二次世界大戦の記憶があまりにも強烈で、このときの革命の記憶は影をひそめているのだと。しかし、この革命の失敗があったからこそ、このあとの時代へと繋がっていくわけで、ドイツ革命を語らずにその後の歴史を語ることはできないのだろうと思う。だからこそ作者はこんなにもページを割いて1919年の出来事を克明に綴っているのだ。
ヤングアダルト向けということだが、決してその内容は軽くない。
第一次世界大戦が終結し、戦争に行っていた兵士たちが帰ってくる。「お国にために戦うのだ」という誇りを胸に戦争に行った兵士たちは、戦争の現実を目の当たりにし、傷つきぼろぼろになって帰ってくる。主人公ヘレの父親も身体と心に深い傷を負って帰ってくる。失くしたのは腕だけではない。
そして戦争は終わっても一向に暮らしは良くならない。貧困と殺し合いは止まない。この状況をかえるためにはどうしたらいいのか。革命といったって結局のところは殺し合いと変わらないのではないか。血を流さなければ、犠牲を払わなければ、この流れを変えることはできないのではないか。
つらい物語なのだが、主人公であるヘレという少年の視点から語られているため、子どもの持つ強い生命力が底に流れていて、絶望だけではなく「希望」も感じさせてくれる。(それが叶うかどうかはまた別の話なのだが)
本当につらい時に、子どもは希望を与えてくれるということはよく言われるけれど、読んでいると本当にそのことを痛感する。戦争のさなかでもクリスマスを楽しみにし、人の優しさを喜び、不正や欺瞞に怒り、自分の失敗を悔やみ、何もかもを見届けようとする。
おそらくこの小説がヤングアダルト向けに書かれているということには、いろいろな意味があるのだろうと思う。
わかりやすいこと。広く読まれること。そして悲惨な状況や出来事を正確に伝えながらも決して希望を失わないこと。
第二部はいよいよヒトラーの時代に突入する。どれだけ酷いかということを知っているだけに読むのが怖い気もするが、しっかり見届けようと思う。